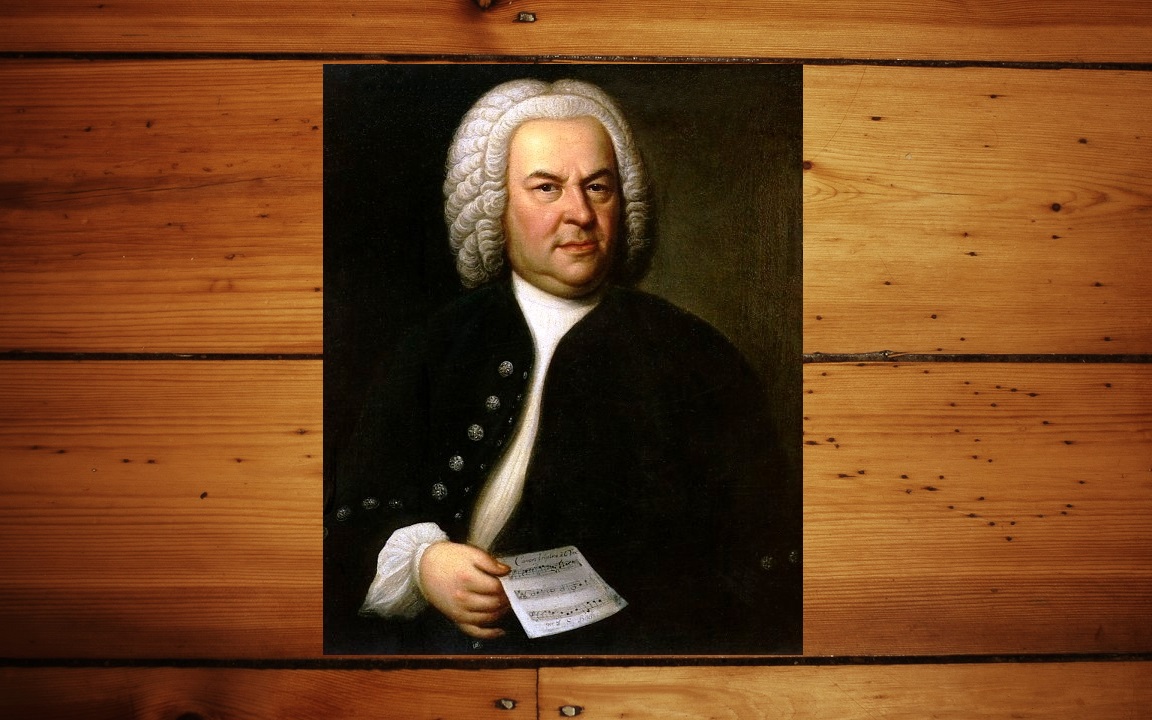フェルデンクライス・メソッドを知っていますか?
名前も聞いたことがない人がほとんどだと思いますが、実は全ての音楽家が知っておくべき知識と言っても過言ではありません!
痛みがなくなり、身体を動きやすくし、テクニックを大幅に改善できるので、人によっては人生が変わるぐらいの効果があります。
じゃあ、なんで知られてないのかってことですが、これは創始者の人にちょっと・・・いや、かなり責任があります。
モーシェ・フェルデンクライス博士(1904-1984)という人なんですが、彼自身がこのように言っています。
"I was irritated by my inability to explain in a few words exactly what I was doing."
自分がしてることを、うまいこと説明できへんのが、めっちゃ腹立ったわ。
(*フェルデンクライス博士の言葉は直訳するとかなり難解な日本語になるので、全てわかりやすく意訳しております。)
- Moshe Feldenkrais. Elusive Obvious. Meta publications, 1981, p.90
もちろんこれは特定の文脈における発言ですが、基本的に彼は、自分の考えたことを人に伝わりやすい、わかりやすい言葉でまとめるのが苦手だったようです。
そんなわけで、普通の人が聞くと「ちょっと何言ってるかわからない感」があって、なかなか一般には広まりにくいみたいですね。
しかし、もし彼の言いたかったことが理解できれば、そのアイデアが圧倒的に本物で、すさまじい可能性を開いてくれることに気付かれるはずです!
カラダ♮で紹介しているフィジカルトレーニングも全て、フェルデンクライス・メソッドを応用して、わたしが考え出したものです。
というわけで今回は、フェルデンクライス・メソッドとは何か、できるだけわかりやすく説明しましょう!
その本質だけを取り上げて、なおかつ音楽家にとってどのように役立つかをお伝えしますね。
(参考文献として、フェルデンクライス博士の生涯最後の著作”Elusive Obvious”を軸にしてお話します。)
この記事はカラダ♮のYouTubeで発信している動画の内容を記事に直したものです。
映像を見た方がわかりやすい所も多々ありますので、ぜひ動画も参考にご覧ください!
フェルデンクライス・メソッドの本質
フェルデンクライス・メソッドの本質は3つにまとめられます!
1.人間の活動は脳の自動反応。
脳と身体中に張り巡らされている神経を合わせて、専門用語で神経系と言います。
この神経系がわたしたちの全ての活動をコントロールしています。(ここではわかりやすさのために「脳」と呼びましょう。)
わたしたちが、動くのも、考えるのも、何か感じるのも、何かの感情を抱くのも全て、脳が電気信号を受け渡しあっているんです。
こう聞くと、じゃあ人生は電気信号でしかないのかとなりがちですが、科学理論とは物事の一つの捉え方です。
恋人の作ってくれたアップルパイを見て「これは原子、分子の結合でしかない」とは思わないですよね。
物事にはさまざまな捉え方がありますが、最もシンプルで、考えを発展させるのに便利なものを科学は採用します。
そして、脳は電気信号をよく通すところに、より通りやすい道を作ります。
このような脳の性質は、専門用語で「脳の可塑性」、「ヘブ則」として知られています。
*脳の可塑性=脳が変化し、変化を保つ性質
*ヘブ則=同時に発火した神経細胞は結合が強まる。
脳が良く使う道をより通りやすくしてくれるので、わたしたちは最初はできなかったことも、繰り返していく内に慣れていき、最後は簡単にできるようになるんです。
さらに、いったんできてしまった通り道を脳が使うのは、ほとんど自動的に行われます。
わたしたちが立ち上がる時、一々立ち上がり方を考えないですよね?
また、鳴かぬなら鳴くまで待とう・・・ホトトギスですよね?ここで「フラミンゴだったかな?」とはなりません。
他にも、スーパーでレモンや梅干を見てつばが出る時、よしつばを出そう!と思っている人はいませんよね?
これらの例は、すでにわたしたちの脳にある、電気信号が通りやすくなった道を示しています。
まとめると、人間の全ての活動は、脳の電気信号の受け渡しであり、そのほとんどは自動的な反応です。
そして、フェルデンクライス博士は、この科学的事実を踏まえて次のような指摘をしています。
"Conscious control and willpower, when properly directed, often improve certain details here and there, but intellect is no substitute for vitality. A sense of the futility of life, tiredness, and a wish to give it all up is the result of overtaxing the conscious control with the tasks the reflexive and subconscious nervous activity is better fitted to perform."
めっちゃ意識して考えたり、気合でなんとかしようとしたら、ちょっとしたことはようなるで。
けど、頭使っても結局はできるようになれへんねん。
「なんかやっても無駄ちゃう?」とか、「しんどいわぁ、もう全部やめたいわ」ってなるんはな、本来無意識で勝手にやるもんを、意識で無理にコントロールしようとするからやで。
- Moshe Feldenkrais. Elusive Obvious. Meta publications, 1981, p.69
この言葉だけでも、わたしたち音楽家の世界を揺るがしてしまいます!
彼の言葉を音楽家向けに翻訳すると、「良い演奏ができるかどうかは脳の自動反応によるよ。やろうと思ってやれるもんではないし、がんばっても疲れちゃうよ。」ってことなんです。
それでは次は、その自動反応の、電気信号の通り道はどのように作られるのかを見ていきましょう。
2.分かる。
脳の通り道がどのように作られるか、それを理解するためのキーワードは「分かる」です!
まずはフェルデンクライス博士の言葉を見てみましょう。
"The baby cannot play the violin.
One of the reasons is that the impulses are not differentiated sufficiently and the motor activity is not differentiated either.
The responses and the intentional acts are global, not graded. All the members, hands and legs, move together and cannot form any finely directed act.
Later, when the growth and the functioning gradually form a more specific passage for individual impulses in the synapses, more varieties of movement become possible.
The fingers can be moved separately from one another.
Different rates and intensities can be produced even in parts of the fingers.
This discrimination between similar but slightly different movements is the differentiation we mentioned."
赤ちゃんはバイオリン弾かれへん。
脳の信号がまだちゃんと分かれてへんから、反応とか行動が全部ざっくりしてて、細かい調整なんかできひんのや。
せやから、手とか足とか全部一緒に動いて、こまごました動きなんか全然無理やねん。
でもな、成長していって、信号が脳の中で個別に通るようになってくると、だんだんいろんな動きができるようになるんや。
指を一本ずつバラバラに動かせるようになったり、指の一部だけで違う速さとか強さの動きができたりするんやで。
こうやって、似てるけどちょっと違う動きを区別できるようになるんが、「分化」っちゅうことやねん。
- Moshe Feldenkrais. Elusive Obvious. Meta publications, 1981, p.129
ここでフェルデンクライス博士が言いたいのは、人間が何かできるようになる、というのは、脳の中で、大ざっぱに一つの通り道だったものが、特定の通り道に分かれ、それぞれを独立させられることなんだということです。
これは現代科学においても、神経細胞同士がつながり、そのつながりがミエリンという絶縁体に覆われ、情報伝達を速くする現象として解明されています。
身近な例で実感してみましょう。5本指全部を曲げ伸ばしするよりも、どれか1本の指だけを曲げ伸ばしする方がたいへんですよね?
1本指だけ動かす方が物量としては軽いはずですが、脳の働きとしてはより分かれた、特定の通り道が必要になるのでたいへんに感じるんです。
まばたきなども同じです。まぶたが閉じられない人はいないと思いますが、ウインクができないという人は一定数いますよね。片方のまぶただけに指令を通すのは、神経の通り道が分かれていないといけません。
そしてこれは、少し考えてみるとゾッとするほど人生全てに適用できてしまいます。
左右を間違えたり、味音痴であったり、その人特有の地雷ワードがあったり、人種差別なんて問題も・・・また、私の母がミエリンと言おうとして何度もエミリンと言ってしまうのも、すでにできてしまった脳の大ざっぱな通り道があり、それを特定のものに独立させられない、すなわち、”似てるけどちょっと違う”ものを脳が分けられない問題なんですね。
私たち音楽家で言えば、音感が良い人、音楽表現が豊かな人、脱力できる人は、要するに脳の通り道が細かく分かれている人なわけです。
微妙な音程の違いがわかる人、またffとppの違いだけでなく、タッチやニュアンスの違いがわかる人、そして身体全体に力を入れてしまうのではなく、力を入れる所と抜く所の違いがわかる人ということです。
ちなみに、日本語では「わかる」を「分ける」と書きますよね。漢字を考案した人たちはこの”脳の分化”の現象になんとなく気付いていたのかもしれませんね。
フェルデンクライス・メソッドの本質その2をまとめると、わたしたちが何かをできるようになる、分かるというのは、物理的に脳の中の通り道が分かれる現象だということです。
3.分かったら選べる。選べたら自由になる。
そして脳の通り道が分けられると、自由になります。
日本語の「自由」という言葉は色んなニュアンスを含んでしまうので、ここでの「自由」が具体的に何を意味するのか、体験から入りましょう!
1.まず左を下にして寝てください。頭を左腕にのせた状態で、左腕をまっすぐ上に伸ばしましょう。右脚を左脚の前に出しておいてください。
2.その姿勢で完全にリラックスできるように、身体の位置を微調節しましょう。
3.左手を閉じたり開いたり、一定のゆっくりしたペースで動かし続けましょう。
4.その左手の動きを保ったまま、ゆっくり仰向けになってください。
5.今度は、左手を動かし続けながら、元の左向きの姿勢にゆっくり戻っていきましょう。
6.リラックスして、左手の動きを保ちながら、仰向けになったり、左向きに寝たりを繰り返してください。
さて、それでは立ち上がって、右腕と左腕を感じ比べてください。
いかがでしょうか?左腕の方が軽く感じませんか?また片方の手ずつ天井に向かって上げてみてください。明らかに左手の方が楽に上がりませんか?
それこそが、フェルデンクライス博士が言う「自由」です。
ここでフェルデンクライス博士の言葉を見てみましょう。
"Learning that allows further growth of the structures and their functioning is the one that leads to new and different ways of doing things I already know how to do.
This kind of learning increases my ability to choose more freely."
成長していくための学びっちゅうのはな、今すでにできることを、もっと新しいやり方とか違うやり方でできるようになることやねん。
こういう学びがあると、選べる幅が広がって、もっと自由にできるようになるんや。
- Moshe Feldenkrais. Elusive Obvious. Meta publications, 1981, p.35
先ほどのエクササイズには、手をグーパーする動きと、寝返りをうつ動きしかでてきませんでした。
どちらの動きもわたしたちが今まで生きてて何回やったかわからない動作ですが、それぞれの動作を干渉しないように独立させてやるのは、全く”新しいやり方、違うやり方”ではなかったでしょうか?
その学びによって、脳の通り道は細かく分かれ、脳はより洗練された動き方を選べるようになるので、わたしたちが何も意識せずとも自動的に、腕が簡単に上がるようになるのです。
つまり、脳には生来的に学ぶ性質があり、選択肢を増やすことで、より自由になろうとしていると言えるのです。
私たち音楽家は日々、もっと上達しようとして研鑽を積んでいるわけですが、何を目標としているでしょうか?
たとえば多くのバイオリニストにとって、Y.ハイフェッツは一つの到達点かと思いますが、YouTubeで”Heifetz imitation”と検索すると彼が下手な演奏を真似して生徒たちを笑わせている動画を見れます。
つまりハイフェッツは、上手に弾くか下手に弾くかを選べる、すなわちどのように弾くかの自由を持っていたと言えます。
またC.サン=サーンス作曲の「動物の謝肉祭・ピアニスト」では、演奏者はわざと下手な演奏を求められますが、素晴らしいピアニスト達は見事に初心者の手つきを実現してみせます。
しかし、この逆はあり得ないのがわかりますか?
達人は初心者の真似ができますが、初心者は達人の真似を決してできません。
つまり、達人は初心者に比べて、より選択肢がある、すなわち自由なんです。
そうすると、わたしたちは「自由」になることを目指す練習をしなければいけません。
繰り返しだけに頼って、完璧な音楽再生装置になろうとするのは脳の性質に適っていないということですね。
"They think willpower is the real way to achieve correct functioning, and consider that repeated attempts will ensure excellency.
In fact, exercising for the correct final state only produces familiarity and makes any errors habitual."
みんな、意志の力さえあれば正しい動きができるようになるって思ってるし、繰り返し練習したら完璧になるやろって考えてるねん。
でも実際はな、正しい形ばっか意識して練習するんは、それっぽいもんになるだけで、ミスする癖がついてしまうねん。
- Moshe Feldenkrais. Elusive Obvious. Meta publications, 1981, p.32
もちろん、繰り返し練習に意味がないわけではありません。
特に、まだ脳に大ざっぱな通り道すらできていない時期、つまり幼少期における繰り返し練習は大きな意味があります。
しかし、一たび大ざっぱな通り道ができてしまったなら、それを分けて、独立させていく意図の練習をしないと、必ず壁にぶち当たってしまいます。
音楽家にとってどんな意味があるの?
さて、以上の3つの本質から、フェルデンクライス・メソッドとは脳を変化させる方法論なんだと理解できたでしょう。
どこでどんなフェルデンクライス・メソッドの説明を聞いても、これら3つを思い出してもらえれば、とてもわかりやすくなると思います。
それでは、この方法論は音楽家にとってどんな意味があるんでしょうか?
さまざま挙げられますが、最も大きいのは「才能」を解き明かせることです。
私の知る限り、多くの音楽家が人知れず才能の限界に苦しんでいます。
これは音楽を愛し、真剣に音楽に向き合った人ほど、いわゆるプロやセミプロの人達ほど切実に感じていると思います。
決して努力では覆らない何かを、とことんまで努力した人は痛感します。
しかし、それは才能の限界ではなく、自分の脳の使い方を知らないだけだとしたらどうでしょうか?
もしも本当は、自分を根本から変えられ、どこまでも成長し続けられるならば、今どんな現状だったとしてもへっちゃらではありませんか?
私自身、間違った努力のせいで全く指が動かなくなったところから完全に回復し、今はギタリストとして自分の将来に希望を持ち、夢を持てています。
この希望こそが最大の意味です!
カラダ♮の理念
モーシェ・フェルデンクライス博士は、とてつもなく広範囲の科学的知見から、脳の働き、それも人間特有の高度なものについて解き明かそうとしました。
そして、理論を確立していく中で、脳の通り道をどのように分けるかの具体的方法も600通りぐらい考え出しました。
それらのほとんどは身体の動きを使ったもので、フェルデンクライス・メソッドのレッスンとして、世界中で実践されています。
そしてこのチャンネル、カラダ♮では、フェルデンクライス博士のほぼ全ての著作とレッスンを踏まえた上で、音楽家のためのオリジナルのフィジカルトレーニングや役に立つ知識を発信しています!
フェルデンクライス・メソッドを土台にした動画講座、「ゼロから始める演奏家のためのフィジカルトレーニング」も現在制作中です。
ぜひ理解を深めるために、カラダ♮の他の情報もチェックしてみてくださいね!
読みやすさのために、かなり説明を割愛した所もあります。 この記事だけでも意味がわかるように書きましたが、関連分野の予備知識があるとより深く納得できるとと思います。